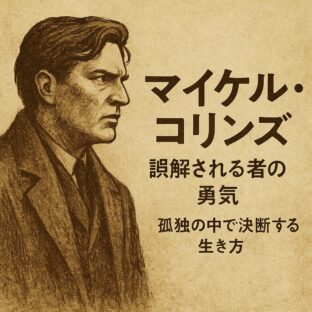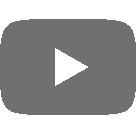【第6回】『マイケル・コリンズ』──誤解される者の勇気 孤独の中で決断する生き方
【第6回】『マイケル・コリンズ』──誤解される者の勇気 孤独の中で決断する生き方
マイケル・コリンズは、アイルランド独立の象徴と語られる。
しかし、映画を“思想の視点”で読み解くと、
彼は英雄ではなく、
「孤独の中心に立つ者」
として描かれていることに気づく。
コリンズは仲間からも理解されなかった。
大義は語っても届かなかった。
裏切り者のレッテルを貼られ、
陰謀に翻弄され、
最後は味方の銃弾に倒れる。
その姿は、
“正しさ”を選んだ者よりも、
“誰にも伝わらない正しさ”を抱えた者の孤独そのものだ。
■ 仲間にさえ伝わらない“大義”
マイケル・コリンズの大義は、
仲間の多くに受け入れられなかった。
暴力革命から政治交渉へ。
敵との妥協。
未来のための“いま”の割り切り。
そのどれもが、理屈では理解できても、
感情では裏切りに見える。
コリンズが抱いた大義は、
理性よりも“未来の痛み”を見据える眼だった。
しかし未来を見る者は、現在の人々に理解されない。
彼の大義は正しかったかもしれない。
だが「正しさ」は時代と人間の感情に押し潰される。
未来を守るために現在を犠牲にする者は、
現在に生きる人々から必ず誤解される。
■ 裏切り/誤解/孤立──“仲間の刃”の方が深く刺さる
コリンズは、敵より味方に傷つけられた。
革命家たちの仲間意識は強く、
その内部で“裏切り者”と見なされることは、
敵に撃たれるよりも深い痛みになる。
信じ合う仲間の刃は、敵の刃より鋭い。
コリンズはその痛みを知っていた。
それでも沈黙した。
それでも前に進んだ。
彼の孤独は、
大義を語る者の孤独ではなく、
“誤解される者の孤独”だった。
理解されない。
伝わらない。
そしてそれでも、歩く。
孤独の中心とは、
自分が選んだ場所ではなく、
大義が自分を立たせる場所だ。
■ 群れの中心ではなく、“孤独の中心”に立つ英雄
英雄とは“群れの中心に立つ者”だと思われがちだ。
しかしコリンズは違う。
彼は群れを率いたのではない。
群れの外で、
“孤独の中心”に立ち続けた。
-
誰にも理解されない決断
-
批判と疑念に満ちた空気
-
一人だけが見える未来
-
仲間の怒りを引き受ける覚悟
-
歴史の転換点の負荷を一人で背負う重さ
この構造は、
瀬尾孫左衛門や寺坂吉右衛門とも異なる。
孫左は“内側の影”
寺坂は“外側の継承者”
だがコリンズは、
“中心の孤独”を生きた者だ。
つまり、群れの内側でも外側でもなく、
誰にも寄りかかれない場所を歩んだ者。
孤独には階層がある。
コリンズは、その最上層にいた。
■ 誰も理解しなかったのに、若者たちが継いだ“精神”
皮肉なことに、
コリンズが死んだ後、若者たちは彼の精神を継いだ。
彼の死は決して報われてはいない。
しかし精神は未来へ届いた。
ここに、
“誤解された者の最後の救い”がある。
死後に理解される者はいる。
死後に継承される者もいる。
理解されない生涯を生きた者の精神が、
未来の誰かに火を灯すことがある。
コリンズの火は、アイルランドの若者たちに受け継がれた。
それは、
誤解されても歩いた者の火だ。
人生には、
「いま理解される火」と
「未来に届く火」がある。
コリンズが抱いていたのは後者だ。
■ 私の人生構造とコリンズが交差する点
ここまで書いてきて、
私がこの映画を “師匠から観ろと言われた理由” も
自然と浮かび上がってくる気がする。
私は
-
誤解される
-
意図が伝わらない
-
孤独のまま決断せざるを得ない
-
大義を言葉にしても届かない人がいる
-
仲間の中に反発が生まれる
-
「正しさ」より「未来」を見ている
-
一人で責任を負ってしまう
という構造の中に、長く立っている。
私は孫左でもあるし、寺坂でもある。
そして同時に、
“コリンズの構造”も背負っているのではないか。
孤独の中心に立つ者だけが見る景色がある。
その景色は、多くの場合、
いまではなく“未来”に属する。
コリンズは、その未来のために誤解を受け続けた。
私の歩みもまた、
その延長線上にあればいいが…。
関連情報