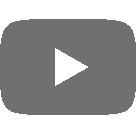増長と増長癖――思い上がりがもたらす落とし穴
増長と増長癖――思い上がりがもたらす落とし穴
増長とは?
「増長(ぞうちょう)」という言葉を耳にしたことはありますか?
先日その言葉を聞きました。
ある部署のある社員が、担当する極く狭い分野で ずば抜けた成功を収めたとする。
当人は 他の分野でも敵なしだと思い込み、業界での流行を追い、仕事の領域を広げようと のめり込んでいく。
幹部クラスには、同様に新たな事業分野に手を拡げる人間も多い。
だが、そのためには経営能力と専門知識が必要なことをつゆ知らず、猪突猛進する人もいる。またはそれをさせようとする上長もいる。
本来の意味は「思い上がること」「謙虚さを失って自分を過大評価すること」です。
仏教では「慢心」の一種とされ、人間関係や成長を妨げるものとして強く戒められてきました。
特に「七慢(しちまん)」と呼ばれる心の在り方の中に「増上慢(ぞうじょうまん)」があります。これは「自分は悟りを得ている」と錯覚してしまう心で、慢心が極端に膨らんだ状態を表しています。
つまり「増長」とは、心のバランスを崩した“思い上がり”そのものなのです。
先日の話は、「●●氏は、増長癖があるよね」という流れだった。
増長癖とは?
「癖」がつくと、それは習慣化します。
一時的な思い上がりなら誰にでもありますが、それが「増長癖」になると無意識に繰り返してしまうようになります。
-
仕事の例
昇進した途端、部下の意見をまともに聞かず、「自分が一番正しい」と押し通す上司。 -
学びの例
本を数冊読んだだけで「自分は専門家だ」と思い込み、知識を誇示して周囲を見下す人。 -
家庭の例
家族に支えられて得た成功を「自分の努力のおかげだ」とだけ考えてしまう夫や妻。
これらはすべて「増長癖」の典型例です。
増長の特徴
増長や増長癖には、いくつか共通する特徴があります。
-
自分の考えや立場を過大に評価する
-
他人の意見や助言を聞き入れにくい
-
成果を自分だけの力と錯覚する
-
態度が横柄になり、人間関係を悪化させる
小さな成功体験が“慢心”を育て、その繰り返しが癖になる。気づかぬうちに周囲から敬遠されてしまうのです。
増長を防ぐためにできること
では、増長を防ぐにはどうすればよいのでしょうか。
-
謙虚さを意識する
成功の裏には必ず他者や環境の支えがあることを思い出す。 -
周囲の声に耳を傾ける
「なるほど、そういう見方もあるんだ」と受け止める習慣をつける。 -
感謝を口に出す
「ありがとう」を言葉にすることで、心が自然と整います。 -
自己点検を習慣にする
1日の終わりに「今日は増長していなかったか」と振り返る。
「増長」は誰にでも起こり得る自然な心の動き。
ただし、それが「増長癖」として定着してしまうと、本人の成長を止め、周囲との関係を壊してしまう。
関連情報