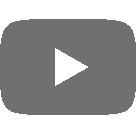出版詐欺から身を守れ!──その出版社、本当に信頼できますか?
出版詐欺から身を守れ!──その出版社、本当に信頼できますか?
「出版できると思ったのに…」という相談が増えています
出版は、多くの方にとって人生の目標のひとつです。
自分の思いや経験を形にして、多くの読者に届けたい。そう願って出版を決意する方は少なくありません。
しかし、そんな「著者の想い」に漬け込んで、高額な費用を請求したり、内容の確認もせずに出版を急がせたりする出版社や出版ビジネスが存在することをご存じでしょうか。
最近、私の元にも立て続けに出版被害の相談が寄せられています。
いずれも、「信頼していたのに、こんなことになるなんて……」という言葉から始まります。
実際にあった“出版被害”の実例
昨年、ある方から出版のご相談をいただきました。原稿はすでにあり、「秋から書き直して、来年(辰年)に出版したい」とのこと。仕様やスケジュールを相談し、口頭で合意が取れたので仮編集まで進めました。
しかし、契約書にはなかなかサインがもらえず、本格的な編集作業には入れませんでした。
そして2か月後、突然「他社から出すことにした」との連絡が──。
のちにわかったのは、出版先が私がかつてゴーストライターを務めていた会社であったということ。
その出版社の内情を知っていたからこそ、正直、複雑な気持ちになりました。
当時は「有名な会社なら著者にとっていいのだろう」と思い、自分を納得させましたが、今は違う考えを持っています。
出版を通して「著者がブランドを築ける」ことが本来あるべき姿です。
しかし現実には、「著者のブランドを利用する」ことしか考えていない出版ビジネスも存在しています。
なぜこうした“被害”が後を絶たないのか?
その理由は、大きく3つあると私は考えています。
-
出版に関する情報の非対称性
著者は「出版のプロ」ではないため、相場や制作工程の正しい知識がない状態で契約を進めがちです。 -
夢を叶えたいという強い想い
「出したい」という強い気持ちがあるため、高額でも契約してしまう、あるいは冷静な判断を後回しにしがちです。 -
“売れる”という甘い言葉
「あなたの本は絶対売れます」「ブランディングします」などの言葉が、契約の動機になってしまうことも。
特に3つ目は、営業トークに過ぎない場合も多く、出版後の販促や流通計画が不明確なこともあります。
次回予告:【第2回】
「見積もりの“落とし穴”──高額請求のワナを見抜く5つのチェックポイント」
では、次回は実際にあった見積もり例や、その内訳をどう読み取るべきか、判断のポイントを解説していきます。
まとめ:出版の第一歩は「信頼できる相手を見つけること」
出版は、一生に一度の経験になることもあります。
だからこそ、焦らず、慎重に、そして信頼できる編集者や出版社と組むことが大切です。
万代宝書房では、著者の想いや原稿の背景を何よりも大切にし、共につくる出版を目指しています。
出版を検討中の方は、ぜひご相談ください。まずは「話を聞いてもらう」ことから始めてみませんか?
関連情報