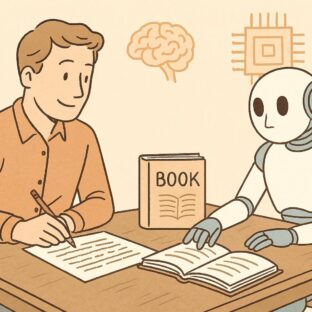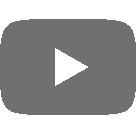第1回:生成AIは本を書けるのか?──その幻想と現実
第1回:生成AIは本を書けるのか?──その幻想と現実
◆「AIに本を全部書かせる時代」が来た?
最近、「生成AIを使えば、あなたは書かなくても本が完成します」といったサービスやセミナーの案内が増えています。
「AIに指示すれば、1冊の本ができる」「もう人間はいらない」──そんな言葉が踊るSNS投稿や広告も少なくありません。
確かに、AIの文章生成能力は年々進化しており、短時間で見栄えのいい文章がアウトプットされるのは事実です。
しかし、それがそのまま「本が100%AIで書ける」ことを意味するかというと、実態はまったく別です。
◆ 実際にAIにすべてを任せたらどうなるか
AIが得意なのは、「過去のデータから予測して最もらしい文章を生成すること」です。
それゆえ、AIが生み出す文章には、平均化された情報・誰もが見たような内容・よくある表現が並びます。
そこに欠けているのは何か?──
それは「主張」「体験」「文体」「構成の一貫性」です。
- 文章が整っていても、読み進めるうちに軸がブレる
- 具体例が薄く、著者の視点が感じられない
- 読後に「で、結局何が言いたかったんだっけ?」となる
こうした原稿は、「文章風の何か」であって、読者の心に残る“本”ではありません。
◆ 本には“構成力”と“思考の芯”が必要
本を書くという行為は、単に情報を並べる作業ではなく、読者をどこへ導き、どんな問いを投げかけるかという「設計」が伴います。
また、どんなに専門的であれ、どんなに平易であれ、書き手独自の視点や意志が感じられなければ、本としての深みが出ません。
生成AIは、あくまで「書かれそうな文章」を返してくれるだけ。
そこには「新しい切り口」「著者の覚悟」「本としての導線」がありません。
◆ AIの能力を誤解した“幻想”が蔓延している
「AIが全部書いてくれる」という言葉の裏には、
・実際は大量の下書きを人間が直している
・素材や方向性は人間が用意している
・完成度を上げるには何十回ものやり取りが必要
…といった裏作の存在が隠されています。
その努力をまるで不要であるかのように見せて「誰でも著者に!」というビジネスが、今広がっているのが実態です。
しかし、本当に読者の心に届く本を作りたいと願うなら、
AIに“全部任せる”という考え方自体が、現実とはかけ離れていることを知る必要があります。
◆ まとめ|AIに任せきるのは「幻想」である
生成AIは素晴らしいツールです。
ただし、それは「人間の思考と判断」があってこそ力を発揮する存在です。
- 「本をAIに書かせる」のではなく、
- 「本をAIと一緒につくる」という意識が必要なのです。
次回は、実際にAIが得意なこと・苦手なことについて整理しながら、
どこまでAIを使えるのか?どこからが人間の領域なのか?を掘り下げていきます。
次回:AIにできること・できないことを整理する
関連情報