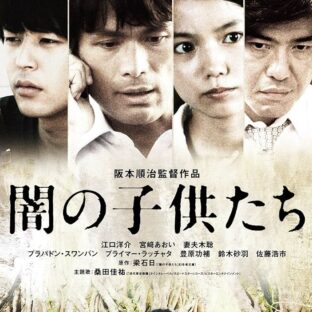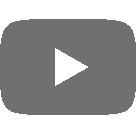あなたが後1年生きることに、何の意味があるのですか?
◆私の持つ、臓器移植問題に見るジレンマについてお話ししたいと思います。
数年前、臓器移植関連で、逮捕者が出た。
これまで、何例も脳死者からの臓器移植が行われている。今後に及んで「脳死は人の死なのか」という議論はナンセンスになってきている感がある。
しかし、このことについて、思考を停止させるのではなく、疑問を持ち続けることは重要なことだと考えている。
臓器移植を受け、健康を取り戻しつつある方に対して、それを見て誰も「あなたは人の命、腎臓を奪ってきた悪魔だ」と言えない。実際、移植を受けた人の立場に立ってみれば、祝福すべきだと思う。
そうすると、「これでイエス!」で思考停止してしまうと、現状肯定になり、その他の疑問が浮かんでこない。法律で肯定されていても、「脳死とか臓器移植に問題点がある」ということは、しっかりとみなければならないと考えている。
脳死臓器移植をどう思いますか?と問われたとき、その答えは、「いや、この前までこう思っていたけど、今はこう思う」等と時の経過ともに、変化してよいと私は思っている。そのために、思考停止させず、疑問をもち、考え続ける必要がある。
ここで、一つ、疑問を投げかけたい。あるドラマのセリフであった。
「臓器移植は、生に対する執着ではないのか。移植までして、この世で生きながらえたいのか。あなたに(その方に)その価値があるのか?」
この質問の意図は、「人間がもつ、欲望のことを抜きに考えてはいけない」ということである。なぜなら、私たち人間の多くは、欲望を捨てろと言われても、捨てられないからである。これにどのような答えを出すのであろうか?
もう一つ、「生命の尊厳」の視点から疑問を投げかけたい。それは、欧米の移植推進派の人たちの考え方の「脳死になっている人は、資源なのか?」というものである。
海外の臓器移植推進国では、脳死になった人は、もう移植の為の資源であり、後はいかにその資源を多く獲得するかということと、資源をいかに有効利用するかということに、みんな必死で努力しているのである。
この考え方になると、後は資源を運用するために、いかにコストを低く押さえるかという、ほとんど流通の話になる。いかに迅速に届けるかとか、臓器を多くの移植を待ってる患者に、少ない脳死の人の臓器をばらして届けるかというような、まるで、コンビニと同じで、いかに流通コストを下げるかという話になる。
資源という考え方でいうと、石炭とか石油と一緒である。
そこで、見失われていくものが、脳死になった人の生命の尊厳なのである。日本も脳死移植が定着していけば、これと同じになっていくと推測される。
生命の尊厳がないがしろにされ、人間の生命が資源化していっている。そのように動いているのが、臓器移植の現実なのではないだろうか。
今の流れでは、日本もこのように動いていくのであり、そこのところを国民が一人ひとりがどう思うのか、どうしていくのか、どう考えていくのかということを、自分事として考える必要があるとあると思うのである。
人間の生命が「資源でいいのか」「脳死になったらその人はもう死んだのだし、もう物体と同じだし、物と同じなんだから有効利用する人の方が倫理的だ」と考えていいのか。
脳死者からの臓器移植の大きな問題は、他人の死を前提とするという点である。
心臓、肝臓、心臓移植の場合は、人は死なないと移植できないわけだから、結局待機している患者さんは、後何ヶ月の内に臓器を貰わないと死んでしまう、ということがある。すると、待っているうちに「早く現れないかな」という気持ちになるのが正直な気持ちであると聞く。「順番が早く回ってこないかな」という気持ちから、寄付を募ってアメリカ等海外に行って臓器移植を受ける。
「早く誰か死なないかな。心臓だけ無事で死なないかな」という心、そうなっていくことに「人間の本性」があると思う。
そして、それに支えられているのが臓器移植医療ではある。それは臓器移植の陰の部分、闇の部分である。
同時に、逆の面もある。
「自分の死んだ脳、死んで生き返らないのだったら、他の元気な部分をいろんな人に役立ててもらいたい」と思うのも「人間の本性」であると思う。その人たちの思いをサポートしていくという面が臓器移植には確かにあるのであり、それは、臓器移植のもっている光の面である。
このように、臓器移植医療の問題を、どう評価するのかは、とても複雑である。なので、その複雑なところを、私たちは、一面的でなく多目的に見ていく必要があると思うのである。「自分の脳が死んでも、他の生きている臓器は役立てて欲しい」という面、あまり大きな声で語られていないもう一つの面「臓器をもらってまでも生き延びたいという欲望をどう考えるか」という側面があるのである。
例えば、重い心臓病、腎臓病の方の場合、全員が移植を望んでいるかというと、そんなことはないのである。腎臓の場合、将来、脳死が仮に移植できるようになったとして、移植を受けたいと希望する人は半分程度であるという調査データもある。このデータは、半分の人は今のままの方がいいと思っていること示す。ということは、移植を望む人はやっぱり臓器をもらってまでも生きたい、またはよい状態になりたいと思っているということの反証になろう。
これは、「健康でありたい欲望」「なるべく長生きしたい欲望」であるが、それを一体どう考えていけばいいのだろうか?
私は高校2年生の保健の授業を受けて、人間の健康ってなんだ、生死ってなんだ、と考えさせられ、そのことをどうしても知りたくなったが、未だにその答えを見い出せないでいるのである。
私は個人的に、高校2年生の時からずっと悩んでいるが、もっと人間がというか、人類がまだまだ時間をたくさんかけて、悩まないといけないテーマだと思うし、悩み続けなければいけないと思っている。
「限りないもの欲望」と井上陽水が歌っていたが、欲望追求ということから我々は逃れられないと思うが、逆に言うと、欲望追求していくことに走ったら、欲望は拡大拡張していくということはわかっている。
もっともっと生きたい、もっとこうしたいという風になる。それで、欲望追求をサポートするように、自分の回りを整理していくと、何が起きるかというと、持っているものを使わなくなる。
例えば、私はカバンが好きである。よく買いたい衝動に駆られる。「このカバン欲しいな」と購入するとする。すると、何が起きるかというと、前に気に入って買った鞄を使わなくなる。いっぱいカバンを買っていると、押し入れにカバンがあふれてくる。
ここで言いたいことは、持っているカバンを使わなくなるというのは、何だろうか?ということである。これは、「持っているものを使わなくなる」ということである。
よく考えると、毎日でも通勤や通学に使いたい、とまで思っていたカバンを使っていない。飽きたからではない。なぜなら、思い出して使うと、やはり感動する自分がいる。
これをどう分析すればいいのだろうか?
欲望追求に進んでいくと、私たちの「もっともっと」という欲望を満足させるが、逆に持っているものを使わなくなるという逆の面も同時に起きるということだと思う。
そして、持っているものを使わないと、逆に、今度は増えていくからカバンの置き場に非常に困る。使わないものを持ち続けていくことに、エネルギーを使うことになる。持ち続けていくことって大変である。
ここに、ポイントがあると私は思う。
つまり、与えられたものを開花するのではなく、この可能性までもつみ取ってしまうのではないか、欲望追求を肯定していくと、今、自分に与えられているもの開花できなくなるのではないか、と考えるのである。
逆に捨てていくことで、既に持っているものを、もっと味わい深く使うという可能性が出てくるとも考えらえると思っている。
この伝でいけば、私は逆に物を捨てることによって、最後に残ったものを深く味わえることがある、と思うのである。断舎利がブームになっているが、その真意は「得ることとは失うこと」といえるのではないだろうか。
移植問題にもこの考え方が当てはまるとすればどうか?
人間が最も欲しいものが健康であり、命であると思う。それによって、得たことによって、大きな何かを失うのではないだろうか。つまり、人間のそもそももっている可能性を摘み取ってしまうのではないかということである。
人間は、生まれたときに必ず決まっていることは、死ぬということである。臓器移植を受けても、やはりいつかは死ぬのである。臓器移植を受けてどうなったかというと、死ぬのが5年延びたとか、30年延びたということであり、逆に言えば、手術により、死期が早まるということもあるのである。
このこと考える中で、人間の尊厳、自分の尊厳、他社の尊厳とキーワードが抜けているような気がする。と言っても、自分はその答えを持っていない。
私は、臓器移植に反対しているわけではない。臓器移植には、こういう面もあるので、多面的に検討する必要があるということを言いたいのである。臓器移植を考える上で、2本の映画を紹介したい。
一本目は、映画『闇の子供たち』である。タイの児童買春と臓器売買がテーマである。タイでは、地方から売られてきた小学生くらいの男の子や女の子が、闇の世界で性サービスを強要されている。その子たちを買春するのは、ヨーロッパや日本などからやってきた児童性愛者たちである。そこで行なわれているのは、目をそむけたくなるような暴力的な性虐待。子どもたちを欲望の道具とする大人たちの姿は、かぎりなく醜い。その情景を、この映画は、危険な水準にまで迫りながら描写した。

映画では、タイのブローカーから心臓を買って、病気の息子に移植させようとする日本人夫婦が登場する。そしてその心臓は、脳死になった子どもから摘出するのではなく、売春施設で使い物にならなくなった子どもから、生きたまま摘出するというのである。その真偽を確かめるべく、危険な取材を開始した新聞記者、南部浩行を軸に、物語は展開する。彼は、しだいに闇の勢力へと迫っていくのだが、それと同時に、彼自身の内面にあるもうひとつの闇が、徐々に姿を現わしてくる。そして、売春組織の行なおうとする悪の決定的な写真を撮影したとき、彼は、自らから押し隠してきたもうひとつの悪にその全身を飲み込まれてしまうのである。
ラスト、一枚の布をはぎ取ったあとに露わになるその情景こそ、南部浩行という新聞記者によって象徴されるところの、我々日本人の自画像にほかならない。それを目撃した観客は、この映画がタイの現実を単に遠くから描いていたのではなく、実は日本に住む我々の精神世界の荒廃を、その内部から暴き出そうとしていたことに気づくのである。だが、ここに描かれたことはけっしてフィクションではない。これは、今なお現実に起きていることである。
映画を見終わった観客は、「それは一部の人間がやっていることであって、この私には直接関係ないことだ」と自らに言い聞かせようとすることだろう。しかしそれは本当にそうだろうか。小中学生の女の子にジュニアアイドルという名称を付けて、Tバックの水着を着せ、ほとんど裸のポーズをさせたDVDを大量に売りさばいているのはいったいどこの国か。「児童ポルノ」に関する禁止法案や条例を作ろうとすると、ネット掲示板では大反対の声で埋まっているのは日本である。
日本もまた、子どもの性を食い物にする文化の例外ではないということ、そして我々の一人ひとりがその文化に巧妙に織り込まれているということ、現状の黙認はすなわち現状への加担に他ならないこと、それがこの映画の真に言おうとしていることである、と私は思うのである。
もう一本は、映画『21グラム』である。「人は死ぬときに21グラムだけ軽くなる」ことから、このタイトルになったようだ。魂の重さなのか。心臓移植や人工授精を題材に、この映画で描かれるのは、人を殺しても、自殺しようとしても、常に生き延びてしまう男と、生き延びるために手に入れた心臓を、自らの手で無残に破壊してしまう男の、壮絶な戦いのドラマである。
心臓病で余命一カ月と告げられたポールに、ある日、交通事故で脳死になった男の心臓が移植される。生き延びたいという欲望は、いつのまにか自死へと反転していくのである。
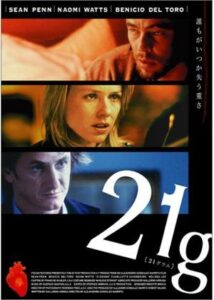
臓器移植問題を法律で決まられたからそれでいいというものではないのである。
生命の尊厳の前に、法律はどこまで介入していいのかを問うていくことが重要なのである。
NPO理事長の逮捕の報道を見て、そんなことを思った。
最後に、自分に、皆さんに問いたい。
「あなたが後1年生きることに、なんの意味があるのですか?」
関連情報