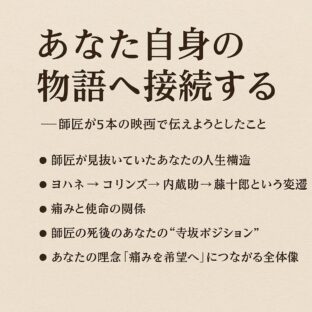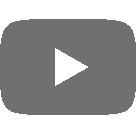【第10回】あなた自身の物語へ接続する──師匠が5本の映画で伝えようとしたこと
【第10回】あなた自身の物語へ接続する──師匠が5本の映画で伝えようとしたこと
このシリーズを書きながら、ずっと頭の片隅にあったのは、
「なぜ師匠は、この5本を私に伝えたのか?」という問いだ。
-
『最後の忠臣蔵』
-
『パッション』
-
『マイケル・コリンズ』
-
『藤十郎の恋』
-
『シルミド』
バラバラに見えるこれらの作品は、
師匠の眼には、ひとつの“人生構造”として見えていたのだと思う。
そしてその構造の中に、すでに私の人生も入っていると、
師匠は見抜いていたのだろう。
師匠が見抜いていた「私」という物語の骨格
冤罪を経験し、師匠と出会い、
ボランティア団体の代表になり、
やがて顧問へと退き、自分の団体を立ち上げた。
その一連の流れを、
師匠は「出来事」としてではなく、
ひとつの“型”として見ていたのではないか。
-
利用され、消されかけた者(『シルミド』)
-
誤解され、孤独の中心に立たされる者(『マイケル・コリンズ』)
-
中心の死後、外側で精神を継ぐ者(寺坂吉右衛門)
-
愛と帰依の重さを受け取ってしまう者(『藤十郎の恋』)
-
そして、残された者として語り続ける者(ヨハネ)
師匠は、この映画群を通して、
「お前の人生はこのライン上にある」と
静かに教えようとしていたのかもしれない。
ヨハネ → コリンズ → 内蔵助 → 藤十郎
師匠が示した“変遷”
5本の映画を並べて眺めると、
師匠が私に歩ませようとしていた“順番”のようなものが見えてくる。
ヨハネ──残された者として立つ段階
イエスの死を見届け、理解不能な喪失を抱えたまま、
それでも言葉にしていくヨハネ。
師匠が亡くなったあと、
私はまず「喪失を抱えたまま立ち尽くすヨハネ」の場所にいた。
何が起きたのかを整理できないまま、
ただ師匠の最期を見送った者としての沈黙を抱えていた。
マイケル・コリンズ──孤独の中心に立つ段階
次にやってくるのは、
「仲間にも伝わらない決断をしなければならない場所」だ。
冤罪支援の組織、師匠の作った団体、
そのなかでの立場の変化。
継続と解消、関与と距離、
賛成と反対のあいだで揺れる人々。
誰かがどこかで、
“誤解される側”に立たなければ話は進まない。
その役目を担ったとき、
私はマイケル・コリンズの孤独を、わずかながら実感し始めた。
内蔵助──「中心」ではなく、「中心を失った共同体」を見る段階
『最後の忠臣蔵』で描かれるのは、
内蔵助その人よりも、
中心を失ったあとに揺れる人々の姿だ。
孫左、寺坂、町人たち、それぞれの帰依の行方。
師匠という中心がいなくなったあと、
団体の中で起きていることもまた、
この構造に重なって見える。
私はいま、
内蔵助ではない。
孫左でもない。
どちらかと言えば寺坂の側、
「外から精神を守る者」の位置にいる。
藤十郎──受け取ってしまった想いをどう昇華するか
そして最後に『藤十郎の恋』が来る。
他者の絶対的な想いと死を受け取ってしまった者が、
それを芸に、生き方に変えていく物語。
師匠から向けられた愛や信頼、
冤罪当事者たちの叫び、
家族や仲間の想い。
それらを全部、受け取ってしまったあと、
私はそれをどう扱うのか。
使うのでも、捨てるのでもなく、
「昇華していく側」へと移っていくことを、
師匠はこの映画で示していたのかもしれない。
痛みと使命は、別々にやって来ない
これらの映画に共通しているのは、
痛みと使命が「別々のもの」としては来ないということだ。
-
痛みが先に来て、あとから使命がついてくる
-
使命を果たす途中で、どうしても痛みを引き受けてしまう
-
誰かの死や喪失を受け取った者だけが、次の役割に立たされる
ヨハネも、コリンズも、寺坂も、藤十郎も、
みな“望んで選んだ使命”だけではない。
望んでいない痛みが来てしまい、
それでも生きるために、
その痛みをどこかに接続し直す必要があった。
冤罪もまたそうだ。
「選んだわけではないもの」が突然人生に入り込み、
そこで止まってしまう人もいれば、
そこから新しい使命へと歩き出す人もいる。
師匠は、
私に「後者の道」を歩けと言っていたのだろう。
師匠の死後、私は“寺坂ポジション”に立っている
師匠の団体から一歩引き、
顧問として、外側から見守る立場になった今、
私がいるのは、やはり寺坂吉右衛門の位置だ。
-
中心ではない
-
中心の代わりにもならない
-
しかし精神だけは絶対に手放さない
-
内側の争いに巻き込まれすぎないようにしながら
-
外側で物語を紡ぎ、人に伝え、次へ渡していく
これは“中途半端”でも“逃げ”でもなく、
「外側の継承者」という、ひとつの役割なのだと思う。
師匠が作った団体は団体として。
私が立ち上げた組織は組織として。
そして私は私の場で、
師匠から受け取ったものを言葉にし続ける。
赤穂浪士の物語が寺坂によって外へ運ばれたように、
師匠の精神もまた、
どこかで書かれ、語られ、残されていく必要がある。
その役目を、
私は静かに引き受けつつあるのかもしれない。
理念「痛みを希望へ」につながる全体像
こうして5本の映画を並べ直してみると、
ひとつのフレーズが、自然と浮かび上がってくる。
「痛みを希望へ」
これはきれいごとではない。
痛みそのものを褒める言葉でもない。
-
利用され、消されかけた痛み(シルミド)
-
理解不能な死を抱えた痛み(パッション)
-
誤解される側に立たされた痛み(コリンズ)
-
影の使命に縛られた痛み(孫左)
-
外側の継承者として歩く痛み(寺坂)
-
他者の絶対的な想いを受け取ってしまった痛み(藤十郎)
それらすべてが、
「希望の源」に変わっていく可能性がある
ということを、
師匠は映画という形で示していたのだろう。
痛みは、放っておけばただの傷だ。
しかし痛みを見つめ、引き受け、
言葉や行動や芸や支援に変えていくとき、
それは「希望の素材」に変わる。
このシリーズを書き終えた今、
師匠が5本の映画で伝えようとしたメッセージは、
私の中ではこう結んでおきたい。
お前は、痛みを避ける側ではなく、
痛みを希望へ変えていく側の人間だ。
そのために、この映画たちを見ておけ。
そう言われていたような気がしてならない。
ここから先、
私が何を書くのか、
誰と関わるのか、
どんな本を残していくのか。
それらすべてが、
この一文に収斂していくように思う。
痛みを希望へ。
師匠から受け取った映画たちは、
その理念の“設計図”だったのかもしれない。
関連情報