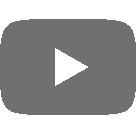【第4回】『パッション』──愛した者を失った時、人は何を抱え続けるのか ヨハネという“残される者”の視点
【第4回】『パッション』──愛した者を失った時、人は何を抱え続けるのか ヨハネという“残される者”の視点
『パッション』は、
イエスの“受難”を描いた物語だと誤解されることが多い。
しかし実際に映し出されているのは、
処刑されるイエスではなく、
残される者たちの表情にこそ物語の核心が宿る。
その中でも、
もっとも沈黙を背負い、
もっとも深い帰依を抱えていたのが、ヨハネである。
ペテロのように震えながら裏切るでもなく、
ユダのように潰れるでもなく、
ただ側に立ち、ただ見守り、ただ抱え続けた者。
彼の姿は、
“中心が消える瞬間に立ち会った人間が何を抱えるか”
を静かに示している。
■ ヨハネは“最も近くにいた帰依者”だった
弟子の中でもヨハネは特別だ。
愛弟子とさえ呼ばれた。
彼の帰依は、
忠誠や信仰を超え、
“この人と共にいたい”という存在の帰依だった。
帰依とは、
理屈ではなく、
存在そのものを預けてしまう行為だ。
ヨハネは、
イエスの思想だけでなく、
イエスという“ひとつの存在”に丸ごと寄り添っていた。
だからこそ、
十字架の下で彼が見つめていたのは
世界の崩壊そのものだった。
中心が死ぬとは、
帰依者にとって“自己の死”に近い。
■ 中心の死を“見届ける者”の役割
ヨハネは逃げなかった。
隠れなかった。
処刑の瞬間にも離れなかった。
これは勇気ではない。
“残される者の宿命を引き受けた者”の姿だ。
残される者とは、
中心の死を目撃し、
中心の沈黙を背負い、
中心の不在を生きる者のことだ。
逃げた者は苦しまない。
隠れた者は背負わない。
中心が死ぬ瞬間に立ち会った者だけが、
深い喪失の構造を抱えることになる。
■ 愛する者の死は、“意味の喪失”として訪れる
ヨハネにとって、イエスの死は単なる別れではない。
-
帰依の中心の死
-
自分を導く存在の消滅
-
意味の源泉の断絶
そして、
生きる理由の破壊である。
『パッション』は宗教映画ではなく、
“意味を奪われた者の表情”を描く作品なのだ。
ヨハネの表情は、
孫左が中心を失った時の沈黙と重なる。
帰依の深い者ほど、
中心の死によって内側から崩れていく。
■ 組織の崩壊ではない。
帰依の崩壊が人を揺らす。
イエスの死後、弟子たちは散った。
逃げる者、失望する者、沈黙する者、語る者。
これは、組織の不和ではない。
帰依が中心を失った時に必ず起こる“自然な反応”だ。
中心は信仰ではなく、彼らの“意味”だった。
意味の死は、
人をそれぞれ違う方向へ散らしていく。
孫左と寺坂が分かれたように、
ヨハネとペテロもまた、
“中心の死の受け取り方”で分かれていく。
帰依とは、本来統一できないものだ。
■ ヨハネの“外側の継承”は、寺坂と同じ構造を持つ
イエスの死後、ヨハネは語り部として歩き始めた。
目撃した者として、
愛した者として、
中心を失ってなお中心を語り続けた者として。
これが、
寺坂吉右衛門とまったく同じ構造である。
-
組織を守る者ではなく
-
名誉を得る者でもなく
-
死で美学を完了させる者でもなく
-
“中心の精神を外側で継ぐ者”
寺坂も、ヨハネも、
“外の継承者”だ。
そしてこれは、私の現在の立場にも似ていると思う。
■ 「自分だけが見届けた」という孤独
ヨハネは、十字架の下に立ち続けた。
この“見届ける”という行為は、もっとも深い帰依の形だ。
見届けた者だけが、
痛みを受け取り、
沈黙を抱え、
未来へ言葉を運ぶことになる。
これは、
孫左の沈黙とは別の沈黙だ。
孫左は“影の継承”
寺坂は“外側の継承”
そしてヨハネは“痛みの継承”
中心が死ぬとき、
その痛みを一番深く引き受ける者がいる。
その者は必ず沈黙を抱え、
それでも歩く。
ヨハネはその道を選んだ。
関連情報