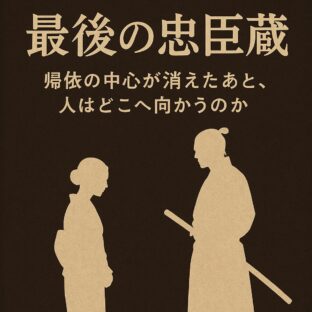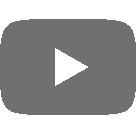【第1回】『最後の忠臣蔵』──帰依の中心が消えたあと、人はどこへ向かうのか
【第1回】『最後の忠臣蔵』──帰依の中心が消えたあと、人はどこへ向かうのか
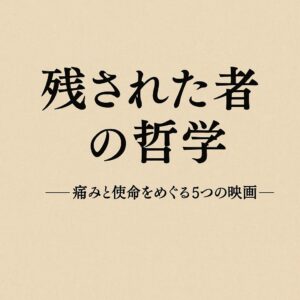
忠義の物語として語られる“忠臣蔵”は、
中心が健在だった頃の話だ。
しかし『最後の忠臣蔵』は、
討ち入りが終わった“あと”から始まる。
ここで描かれるのは、武士の美学ではなく、
帰依の中心を失った人間が、どう生き、どう壊れていくのか
という深い世界である。
“帰依”とは、
誰かに従うことではなく、
誰かに自分の「意味」を預けてしまうことだ。
内蔵助という中心が死んだあと、
残された者はその「意味の断絶」と向き合うことになる。
■ 内蔵助は、赤穂浪士の“主君”ではなく“中心”だった
赤穂浪士は、組織でも派閥でもない。
思想の共同体でもない。
内蔵助その人が、そのまま求心力だった。
中心とは、命令する者ではなく、意味を与える者。
なぜ生きるのか、
なぜ戦うのか、
なぜ耐えるのか。
すべての答えが、内蔵助という“一点”に宿っていた。
だからこそ、
中心の死はただの喪失ではない。
意味の源泉が消えるということ。
■ 密命──可音という“内蔵助の影”が、孫左の帰依を決定づけた
瀬尾孫左衛門(孫左)は、
討ち入りに参加できなかった。
弱いからではない。
不適だったからでもない。
内蔵助が抱えていた、深い影――
愛妾・お艶との間の娘・可音(かのん)の保護を
たった一人に託されたからだ。
これは忠義の任務ではない。
-
主君の弱さ
-
主君の秘密
-
主君の罪
-
主君の愛
それらすべての“人間としての影”を、
孫左は丸ごと預けられた。
これは、忠義では説明できない。
孫左は
“主君の人間性の奥底に帰依した人”
と言うほかない。
■ 人は、理由のわからない使命ほど強く縛られる
密命は説明されない。
目的も語られない。
報酬も、称賛もない。
ただ、
「おまえにしか頼めぬ」
この一言だけが、
孫左の人生を十数年縛り続けた。
ここには忠義の論理はない。
あるのは帰依の心理だけだ。
帰依とは、
理屈で従うことではなく、
“この人のために生きたい”
という、もっと深い衝動である。
理由なき使命ほど、
帰依によって深く浸透し、
人間の骨格そのものを変えていく。
孫左の人生は、理屈ではなく構造で支配されていた。
■ 帰依の中心が消えたあと、孫左は“意味”だけを抱えて生きた
内蔵助が亡くなっても、
孫左は生き続けなければならなかった。
なぜなら、
中心は死んだが、使命は残っていたからだ。
帰依の対象は消えたのに、
帰依によって与えられた役割だけが残る。
これは人を壊す構造だ。
孫左は十数年、
ただ可音を守るためだけに生きる。
しかし可音がついに嫁ぎ、
守るべき秘密が安全に処理されたその瞬間、
孫左は静かに腹を切る。
これは自殺ではない。
「意味の完了が、人生の完了になった」
という、帰依の終着点である。
使命は孫左を生かし、
使命の終わりが孫左の死となった。
■ 寺坂吉右衛門──同じ帰依を抱えながら外側で継いだ者
一方、寺坂吉右衛門は、同じ内蔵助に帰依していた。
しかし彼の帰依は、中心の死を境に別の形へ変化する。
彼は踏みとどまらず、外へ歩き出した。
「中心の死」をきっかけに帰依の対象を“未来”へ移した
と言える。
孫左の帰依は“内側で生きた帰依”
寺坂の帰依は“外側へ広げる帰依”
どちらも同じ内蔵助から生まれたが、向かう方向は全く異なる。
これが帰依の本質だ。
帰依する者はひとつの中心を共有していても、
中心が消えたとき、全員が違う方向に歩く。
忠義なら統一されるが、帰依は統一されない。
■ 『最後の忠臣蔵』は、
「帰依の崩壊」と「帰依の再構築」の映画である
討ち入りは、忠義の物語。
その後は、帰依の物語。
中心を失った者たちが、
-
ある者は使命に縛られ死に向かい(孫左)
-
ある者は精神を外へ運び(寺坂)
-
ある者は形だけ守ろうとし(町人たち)
それぞれに“帰依の残骸”と向き合う。
これは、
私は観てきた、あるいは、属してきた、属している団体の構造とも
驚くほど重なる。
中心に帰依していた共同体は、中心の死後、必ず揺れる。
人は中心がいたときより、
中心がいなくなったときのほうが多様な方向へ散っていく。
帰依が深かった者ほど、
帰依の喪失によって最も深く傷つく。
孫左の姿は、それを象徴している。
関連情報