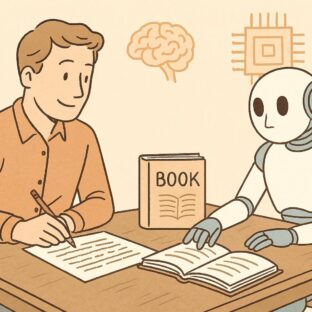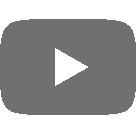第3回:AIを使いこなすには“著者の頭”が必要だ
第3回:AIを使いこなすには“著者の頭”が必要だ
〜生成AIは「思考の補助輪」、主役はあなた〜
◆ はじめに|AIに「全部おまかせ」は成立しない
第1回では、「AIが100%本を書ける」という幻想について。
第2回では、AIの得意・不得意を整理しました。
では、AIを本当に使いこなすには、何が必要なのか?
答えはシンプルです。
👉 「著者自身の頭=思考力・構成力・判断力」です。
AIをうまく活用して書籍を仕上げるには、明確な意図を持って設計する力と、必要な素材を自分で用意する意識が不可欠です。
◆ AIとの共創に必要な3つのスキル
① プロンプト設計力──「どう聞くか」がすべてを左右する
生成AIは、問いかけ方(プロンプト)によって出力の質が大きく変わります。
「何を聞くか」「どんなトーンで返してほしいか」「何文字くらいで」など、入力次第でAIは“別人のように”変化します。
▼ 例:
・「40代経営者向けに、やさしいトーンで『本を書いた方がいい理由』を伝えて」
・「新規性のある切り口で、〇〇の構造を3章立てで解説して」
これができなければ、出てくるのは“汎用的な、誰にも刺さらない文章”です。
② 素材選定力──AIは「何も知らない」前提で使う
AIは膨大な言語データを元にしていますが、
「最新情報」や「現場の空気感」「あなた自身のエピソード」などは一切持っていません。
だからこそ、「本に載せたい具体的エピソード」「自分が体験したこと」「引用したい資料」など、著者が素材を集めて入力する必要があるのです。
▼ 例:
・「このエピソードを第2章に盛り込みたい」
・「私の失敗談をきっかけに展開して」
👉 素材なしで“AIが何かすごいことを生んでくれる”ことはありません。
③ アウトライン構築力──本としての骨組みは人間が作る
書籍は、単なる文章の連なりではなく、読者の理解を助け、考えを深める「構造」を必要とします。
その構造(アウトライン)は、著者が読者の目線に立って設計するものです。
AIは補助的に章立て案を出してくれますが、
👉 「この順番で読ませたい」「ここで一度問いを投げたい」などの設計意図までは読み取れません。
本の一貫性や流れは、やはり人間の構成力が支えているのです。
◆ 「AIと共創する著者」がこれからのスタンダード
AIを“道具”として見たとき、著者には
・なにを伝えたいか(主張)
・誰に届けたいか(読者)
・どう展開したいか(構成)
という3つの「設計」が求められます。
◆ これは、例えるなら「著者=建築家」「AI=大工」
設計図なしにいくら工具(AI)を使っても、良い家(本)は建ちません。
これからの時代、「AIを使える著者」が強くなるのではなく、
👉 「AIと共創できる著者」が生き残っていくのだと思います。
◆ まとめ|AIは“代わりに書いてくれる存在”ではない
本当に価値ある書籍をつくりたいと願うならば、AIは「全部やってくれる存在」ではなく、
👉 「考える著者の“右腕”」として使うべき存在です。
・明確なビジョンを持ち、
・素材を集め、
・情報を整理し、
・伝える順番を設計し、
・そこにAIを“補助役”として投入する。
そうして初めて、“読者の心に届く本”が完成します。
次のステップへ
この3回の連載は、「生成AIは本を書けるのか?」という問いに対して、現実的かつ実践的な視点からお届けしてきました。
今、私は実際にこのテーマで本を執筆中です。
そこでは、より詳細なプロンプトの工夫や、実際の失敗と改善のプロセス、さらに人間の創造性とAIの役割について、具体的な実例を交えながら掘り下げています。
ここではあえて深く語りませんが、もしご興味があれば、今後の出版を楽しみにお待ちください。
あなた自身の思考と構想こそが、AIという道具を最大限に活かす鍵です。
“AI任せ”ではなく、“あなたのビジョンをAIと共に形にしていく時代”が、いよいよ始まっています。
関連情報