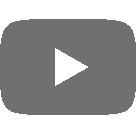◆どんな小さな分野でもいいから世界一の専門家になれ
◆どんな小さな分野でもいいから世界一の専門家になれ
師匠が存命のときの話だが、私のこれから出したい本の企画の相談をしたことがあった。
「来年の本の企画なんですが、出版社から、『数個出してきてほしい。その中か、良いのがあれば、二つか三つ出そう』と言われまして…」
「ほう。それはよかったな」
「はい、それで…」
私はそう言って、六つの出版企画を説明した。

「全部おもしろいな、社会的価値もあるし。でも出版社は、売れるかどうかだからな。出版社がOK出たら、どれをやってもいいと思うよ」
「ありがとうございます」
「お前に一つ言っておきたいことがあるんだが…」
「はい、何でしょうか?」
「お前、本書いていて、楽しいか?」
「楽しいですか? そんなこと考えたこともありません!」
「だよな、それが問題なんだ」
「何が問題なんですか? 食べるために必要だし、私の性分にもあっていると思うんですけど…」
「普通な、本を出す人には、喜びがあるんだ。お前に喜びがあるか?」
「喜びですか…」
「そうだ、喜びだ。『やっと完成したぞ!』とか、『俺が書かねば誰が書く、やり遂げたぞ』とか、『この内容は社会に役に立つぞ、良かった』とか、何かあるだろう?」
「……うーん、ないですね」
「ないよな。お前にあるのは、『あー、本を出せてよかった』だけなんだ」
「……はい、確かのそれは強く思いますね」
「だから、企画が通るとマイナスで、本を出してやっとゼロなんだよ。何冊出しても、ゼロなんだ。それは苦しいぞ。人間、喜びが伴わないと長続きしないんだ」
「そんな、喜びと言われても…」
「そうだよな、喜びを感じられるかどうかテーマにして、本を書けるといい。まあ、頑張れ」
「ありがとうございます。そうします」
「本を一冊出す度に、その分野のそれなりの専門家になっていけ。お前なら、その気になればできるぞ、そのやり方は、すでにお前に教えているつもりだ」
「それは学んでいます」
「で、なあ、お前、一つくらいは世界一になれよ」
「はぁ? 世界一ですか?」
「俺、何か変なこと言ったか?」
「い、いいえ……」
「どんなに狭い分野でもいいんだ。このことは世界で俺が一番知っているという分野を作るんだ。それがある奴はすごいぞ。多くの人はそんなこと考えもしないんだ。あと、何年間もあるんだ」
「……」
「もう一回、言うぞ! どんなに狭い分野でもいいんだ。このことは世界で俺が一番知っているという分野を作るんだ」
「はい!」
「よし、今日はこれでいいか? いいミーティングになったな。また来いよ!」
このことは、師匠が他界した後も頭から離れない。
現時点で、一つだけすごくニッチな世界だが、「このことは世界で俺が一番知っている」と思える分野がある。
あとは、これを社会的に役に立つようにすることが次のテーマだ。
関連情報